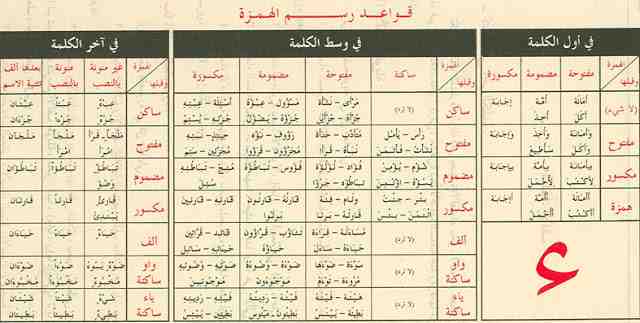
第6夜 ハムザの軽量化
「ハムザの軽量化」( تَخْفِيف الهَمْزَةِ )とは、ハムザが無母音の場合にその子音としての機能を失い、先行の母音と親和する長音化文字に変わる現象である。文法的な観点から見ると、大きく2つに分けられる。一つは単なる発音の訛化と見なされるもので、例えば بِئْر (井戸)が بِير になったり、 سُؤَال (質問)が سُوَال になったりする語形は散見するが、正規形としては認められず、辞書にも採用されていない。しかし、先行の文字がハムザ付きのアリフの場合は特別で、後続のハムザは必ず「軽量化」しなければならない。(「文典」上p27)
では、この現象がどのような場合に起きるかというと、範囲は自ずと限られてくる。まず、ハムザが無母音になるのは、語頭ハムザ動詞の基本形、第4形、第8形及び第10形以外にはあり得ない。更にその中で、先行の文字がハムザ付きのアリフになるのは①基本形動詞未完了形の一人称単数形及び能動分詞、②第4形の完了形全てと、未完了形の一人称単数形、命令形及び動名詞に限られる。i
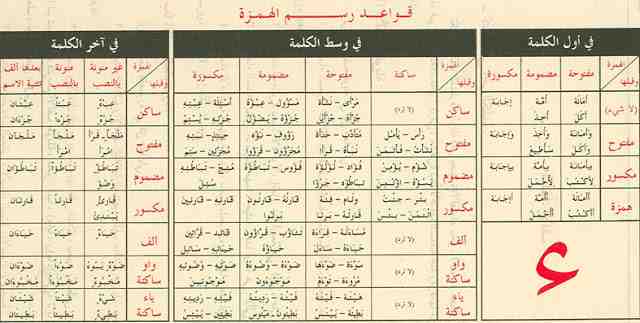
これだけだと話は簡単なのだが、厄介なのは先行文字が「ハムザのないアリフ」、即ち接合のハムザの場合である。この現象が起きるのは2つの場合に限られる。一つは③語頭ハムザ動詞基本形の命令形であり、もう一つは④動詞第Ⅷ形の完了形全てと、未完了形の一人称単数形、命令形及び動名詞の場合である。
③の場合は文法書に解かれているii通りで問題はないが、④第Ⅷ形の場合は様相が一変する。「ハムザの軽量化」を適用する人々と適用しない人々がいるのである。前者の代表格はR・ライトであり、「文典」の中で次の例を示しているiii(「文典」上p111)。
(例1)( اِيتَمَرَ → اِئْتَمَرَ )協議する: أَمَرَ 命令する の第Ⅷ形
(例2)( أُوتُمِنَ → أُوْتُمِنَ )信頼される: أَمِنَ 安全である の第Ⅷ形受動態
ところが、実際の辞書を見てみると、全ての辞書が「ハムザの軽量化」を適用しない語形を採用している。例えば「Hans Wehr」(第4版)には語頭ハムザ動詞第Ⅷ形として5つの動詞、また「ムンジド」(大型判)ではそれに加えて4つ、計9つの動詞が収録されているが、その全てが「 اِئْتَمَرَ 」「 اِئْتَنَسَ 」などとハムザはニブラの上に書かれたままなのである。「リサーン=ル=アラブ」でも同様で、少なくともこの辞書が編まれた 13 世紀末には「 اِيتَمَرَ 」という語形は流通していなかったと思われるiv。なぜこのような対立が生じたのか判然としない。あるいは、アラビア語の歴史を通底するハムザの「守旧派」と「改革派」の闘争史の、現在での局面なのだろうか。
i念のために活用を説明すると、まず①の場合は以下のようになる。
(1)動詞 أَكَلَ の未完了形・1単/能動態: آكُلُ → أَأْكُلُ /受動態: أوكَلُ → أُؤْكَلُ
同・能動分詞: آكِل → أَأْكِل /
次に②の場合を動詞 آمَنَ (信仰する)を例に取ると、次のようになる。
(2)完了形/能動態: آمَنَ → أَأْمَنَ /受動態: أُومِنَ → أُؤْمِنَ
(3)未完了形・1単/能動態: أُومِنُ → أُؤْمِنُ /受動態: أُومَنُ → أُؤْمَنُ
(4)命令形: آمِنْ → أَأْمِنُ
(5)動名詞: إِيمَان → إِئْمَان
ii具体的に説明すると、以下のようになる。まず③では、基本形の命令形は第1語根をスクーンにして、未完了形の特徴母音に応じて母音 [ i ] または [u] を持つ一時性のハムザをその前に立てるので、次のような語形になる。
(6)特徴母音[ u ]: أُومُلُ → اُؤْمُلْ (希望せよ)
(7)特徴母音[ a ]: اِيسِرْ → اِئْسِرْ (捕縛せよ)
(8)特徴母音[ a ]: اِيذَنْ → اِئْذَنْ (傾聴せよ)
iiiまた、この語形を掲げる活用表も散見される。(例えば「201ARABIC VERBS」p14)
iv現在ではどうかというと、例えばインターネットで「 اِيتَمَرَ 」を検索すると、Wiktionaryでは「 اِئْتَمَرَ 」の「alternative form」と説明されている。して見れば、一部では流通している語形と思われる。